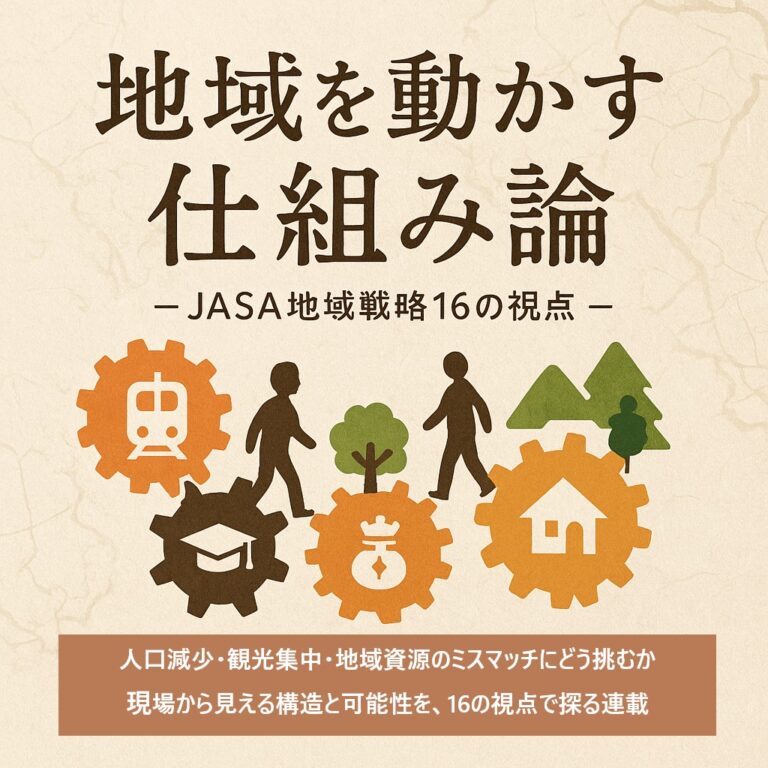1.観光が“浮いた産業”になりがちな理由

観光地としてにぎわっている地域でも、実際に地域経済にその効果がどれだけ根づいているか、疑問の声が少なくありません。地元の若者が観光業を敬遠し、外部からの事業者が主導するツアーやイベントに頼る構造では、「賑わいはあるが、暮らしには届かない」という声が生まれやすくなります。
観光が一時的な収益源にとどまる要因、つまり「浮いた産業」になりがちなのは、こうした“外部依存型”のビジネス構造にあるのではないでしょうか。
当該地域に資本も雇用も残らず、地元の住民が当事者になれない――この構造自体が、観光を地場産業に育てる上での壁になっていると考えます。
2.地場産業として根づかせるには
観光を一過性で終わらせないためには、単なる「体験」や「特産品販売」にとどまらず、継続的な雇用・教育・育成・継承等の視点を取り入れた設計が必要です。
誰が観光事業を担い、誰が次世代に引き継ぐのか。収益の一部が地域の福祉や教育に循環しているのか。こうした問いへの答えを持たない観光事業は、長期的には地域の疲弊を生むリスクがあると考えます。
観光を“売れる商品”としてではなく、“回る仕組み”として組み込んでいくこと。それが地域に根ざした産業へと成長するための視点です。

3.JASAの立ち位置と、これからの問い
JASAでは、観光を“仕掛ける”のではなく、“育てる”視点を重視しています。すぐに答えを出すのではなく、地域と一緒に問いを立て、対話を重ねながら進める。その中で初めて、観光が地域の営みとして根づいていくのではないかと考えています。
観光を持続可能な地場産業にしていくには、どのような準備が必要か。誰とどうやって次世代に残していくか。
JASAはそうした“問いを共有する伴走者”として、それぞれの地域の特性を考えながら、一緒に考え続けていきます。
2025年6月16日
次回予告
次回【視点4】のテーマは「“切り売り型観光”から、地域主体の再設計へ」。
外部主導で消費されがちな地域資源を、地元がどう取り戻し、再設計していけるかを考察します。
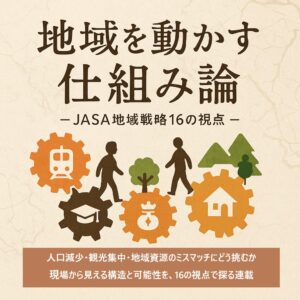
【お問い合わせはこちらまでお願いいたします。】
JASA 日本エリアマネジメント支援協会
info@japan-asa.com