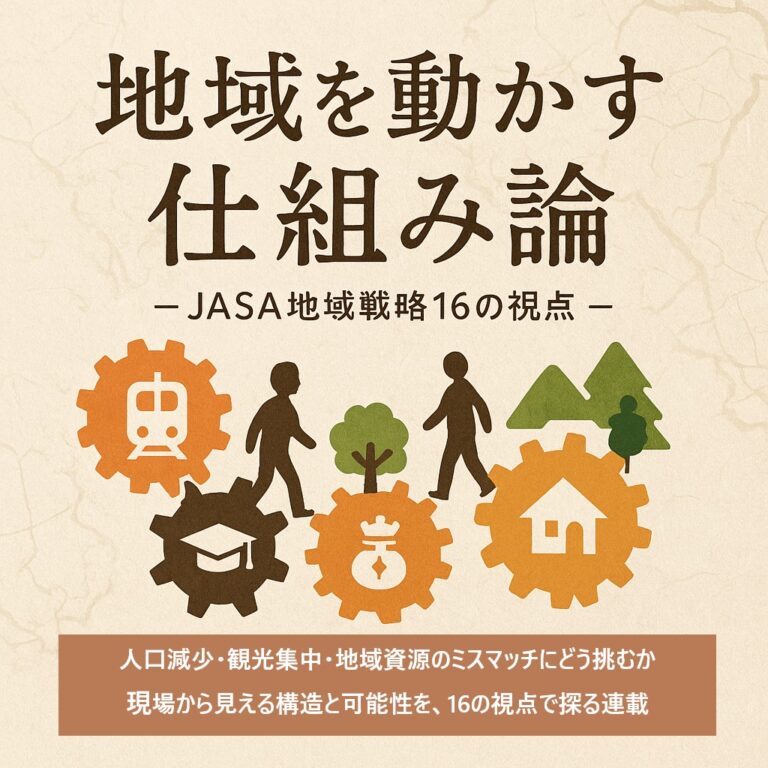1.「誰かに使われる観光」からの脱却

地方の観光地では、外部の旅行会社やプラットフォーム主導で“パッケージ化”されたツアーや商品が出回り、地域は単なる「素材供給地」として扱われる場面が少なくありません。地元の食、景観、文化行事などが、観光の目玉として「切り売り」され、収益の大半が外部に流れる一方で、地元に残るのは、準備・対応・片付けの疲弊や、地域資源が“消費されるだけ”のむなしさです。
この構造の問題点は、単なる経済的流出にとどまりません。地域の人たちが観光に対して「自分ごと感」を持ちにくくなり、誇りや愛着が薄れてしまうのです。観光業が外部主導で回っているかぎり、地元にとっては「使われるだけの存在」となり、持続可能性のない依存構造が深まります。
本来、観光は地域の人々の暮らしと文化が息づくものであり、“誰かに売られる”のではなく“誰かに伝えたくなる”営みであるべきです。観光のあり方を問い直す視点が、いま求められています。
2.「地域が主語」になる設計とは
観光を“誰かが売る商品”から、“自分たちでつくる体験”へと転換するためには、設計そのものを地域が主体的に担う必要があります。これは「地元の声を聞いた」レベルではなく、企画段階から地域住民が参画し、当事者としての役割を果たす仕組みを持つことを意味します。
たとえば、地元の方が観光案内人となり、自分たちの言葉で地域を紹介する“顔の見えるガイド体制”の整備。あるいは、観光収益の一部を地域活動や文化保全に還元する「還流モデル」を導入することで、地域経済への実質的な貢献を可視化する仕組みも有効です。
また、外部事業者との連携が避けられない場面では、地域がガイドラインや価値基準を提示し、「受け入れる側のルール」を明確にすることが鍵になります。こうした合意形成の仕組みを整えることで、観光が地域を“使う”のではなく、“ともに育てる関係”へと変化します。
これからの観光は、「売れるかどうか」ではなく、「続けられるかどうか」が問われる時代です。

3.JASAの視点と“関わり方”の更新
JASAでは、観光を「地域の人が主語になる仕組み」に変えていくことが、地域の持続性や価値の再発見につながると考えています。観光は一方的に“提供するもの”ではなく、地域と訪問者の関係性を築く“対話の場”であるべきです。
しかし実際の現場では、「観光のことは専門家に任せるしかない」といった無力感や、過去に“使い捨て”された経験からくる不信感が根強く残っています。こうした背景を踏まえ、JASAは“関係づくり”を支援する立場として、京都市との事業では、地域住民が主体的に関われるような場の設計や仕組みづくりを提案しました。
今後は、観光の“見せ方”を地域内で議論するワークショップや、「本当にこの体験は地域にふさわしいか?」と問い直す対話の機会など、観光の“編集者”としての地域の役割を強化する伴走支援を行う予定です。
観光の未来は、“売上高”ではなく“関係性の質”によって測られる時代へ。JASAは、その転換期を地域とともに設計していきます。
2025年7月1日
次回予告
次回 #006のテーマは「DX推進、それ本当に地域のため?」。
補助金や流行に流されない、“使えるDX”の見極め方について考察します。
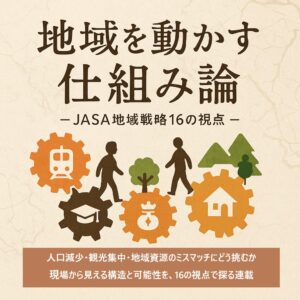
【お問い合わせはこちらまでお願いいたします。】
JASA 日本エリアマネジメント支援協会
info@japan-asa.com