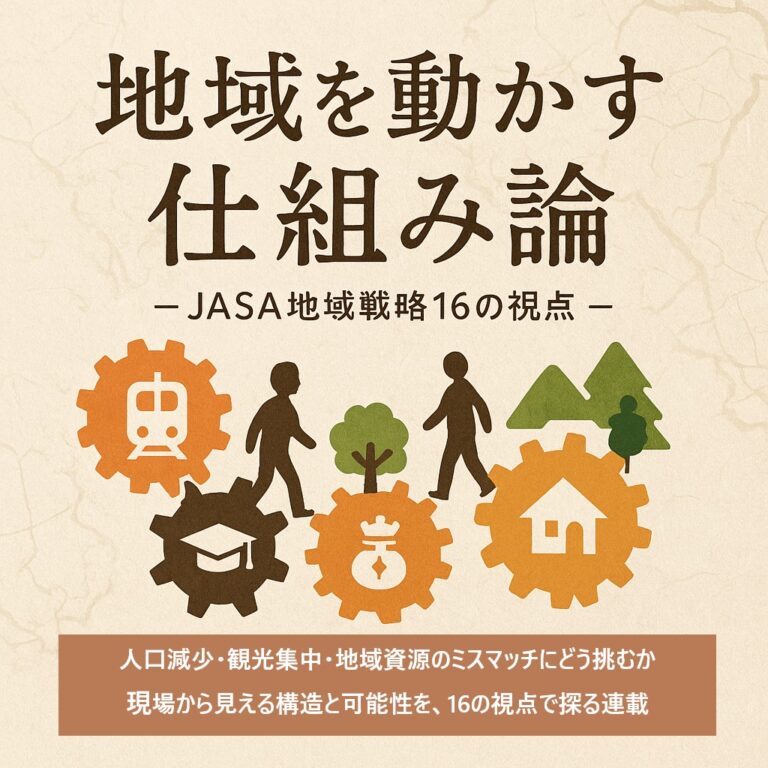1.「伝えること」と「動かすこと」の違い

地域からの情報発信は、広報紙、SNS、プレスリリース、イベント登壇など多様な形で行われています。しかし、“伝えているのに反応がない”“行動につながらない”という課題も多く聞かれます。
その背景には、“伝える=届いた”と誤解してしまう構造があります。発信の本質は、情報を流すことではなく、地域内外の“行動変容”を促すこと。つまり、情報が“誰のために・どこまで届いて・どんな動きにつながるのか”という視点で設計されているかが問われているのです。
単なる通知ではなく、“動かす”ことを見据えた設計こそが、地域発信において真に求められる視点です。
2.発信設計は「仕組みづくり」そのもの
発信は、コンテンツ制作だけで完結するものではありません。むしろ、伝える“内容”と“順番”、届ける“媒体”、受け手の“行動導線”までを含めて設計する必要があります。
たとえば、SNSではただ画像を投稿するのではなく、「どの曜日に、誰向けに、何を訴えたいのか」まで明確にすることが重要です。また、発信は一方向ではなく、コメントやリアクションなどを通じた双方向性が“共感”と“巻き込み”につながります。
さらに重要なのは、発信が単発で終わらず、“連続した物語”として展開されること。地域に暮らす人々が発信内容に重なりを感じ、次のアクションに自然と向かえるような導線が求められます。

3.JASAの視点と“設計の伴走”
JASAでは、情報発信を単なる広報活動ではなく、“地域の動線を設計する仕組み”と捉えています。発信の方法を教えるだけでなく、「何を、誰に、どう届け、どんな動きを期待するのか」まで一緒に考えることが、継続性のある発信につながります。
また、発信の効果は「反応数」だけでは測れません。地域内での意識の変化や、事業者同士の連携、外部からの問い合わせなど、“変化の兆し”を丁寧に拾いながら、次のステップに活かしていく設計が大切です。
地域の文脈に根ざし、声にならない声にも耳を傾ける“発信の伴走者”として、JASAは地域の未来を共に描いていきます。
2025年8月16日
次回予告
次回 #009のテーマは「“地域が主語”になる支援のあり方とは」。
支援する側の論理ではなく、地域の意思に寄り添った支援設計の重要性を問い直します。
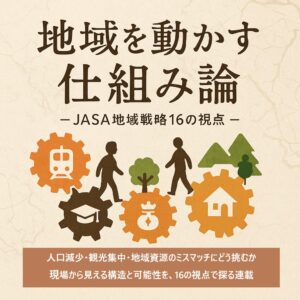
【お問い合わせはこちらまでお願いいたします。】
JASA 日本エリアマネジメント支援協会
info@japan-asa.com