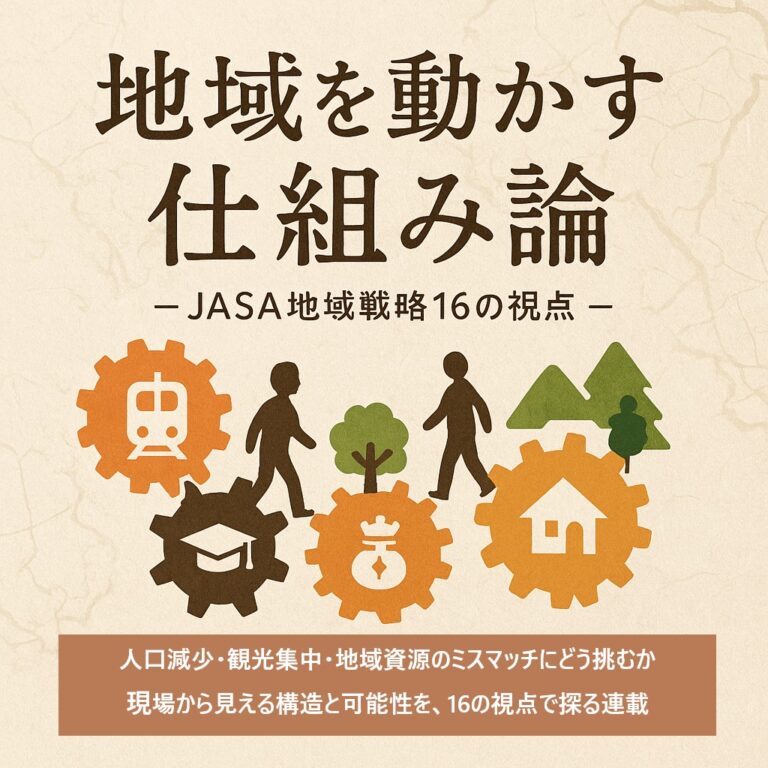1.支援する側の論理が先行すると何が起きるか

多くの地域支援の現場では、“支援する側”の都合で設計された事業や制度と、“支援される側”の現場の状況が食い違うという課題が見られます 。これは、まるでサイズが合わない服を無理やり着せるようなものです。たとえば、地域の実情を考慮せずに、補助金の複雑な要件に合わせた無理な事業計画を立てたり、外部の専門家が一方的に主導するワークショップを開催したりするようなケースです 。
こうした状況は、地域住民が「自分たちの意見が反映されていない」と感じる大きな原因となります 。結果として、支援が表面的なものに終わり、本当に必要な解決策につながらないだけでなく、支援者と地域の間に信頼関係が築けなくなってしまうのです 。この“主語のねじれ”こそが、支援の形骸化を招く根本的な問題です 。
2.なぜ「地域が主語」でなければならないのか
“地域が主語になる”とは、単に住民の声を聞くことではありません 。支援の企画段階から、地域の声を出発点として課題を定義し、計画を立て、進め方を選ぶ、そのプロセス全体に地域の住民が意思決定の主体として深く関わることを意味します 。
例えば、ある地域で空き家を再利用するプロジェクトを進める際、行政や建築家だけで方針を決めるのではなく、地域住民や元所有者と丁寧に話し合う場を設けました 。どんな空間なら使いたいか、どんな機能があれば暮らしに馴染むかを対話の中から探っていったのです 。このアプローチにより、地域の暮らしに根ざしたユニークな活用案が生まれ、利用者の定着率や事業の継続性も向上しました 。
この事例が示すように、支援の質を高めるためには、“問いの出発点”を常に地域に置くことが不可欠なのです 。

3.JASAが目指す「共に考える支援」のカタチ
JASAは、地域支援において、最初から“答えを持ち込む存在”ではなく、地域と一緒に“問いを共有する存在”でありたいと考えています 。
もし、地域から「人手不足で困っている」という声が上がったとします。本当に解決すべき課題は人手不足そのものなのか、それとも、別の視点から見直すことで根本的な構造改革につながるのではないか 。そうした対話を可能にするためには、外部の支援者が「上から目線」ではなく、地域とフラットに向き合う姿勢が求められます 。
JASAは、形式的な合意形成に終始せず、地域の言葉と情熱を出発点とした“共創の場づくり”を重視しています 。住民、行政、事業者それぞれの立場を尊重しながら進める“対話型支援”を通じて、地域が本来持っている力を最大限に引き出すための“聞き方”と“関わり方”を設計し、そのプロセスに寄り添い続ける伴走者でありたいと願っています 。
2025年9月1日
次回予告
次回 #010のテーマは「地域を支える“商工会議所・商工会”の未来とは」です 。
中間支援機能を担う存在が地域に果たす役割と、その強化に必要な視点を考察します 。
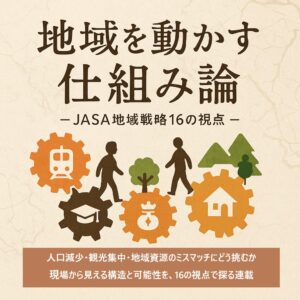
【お問い合わせはこちらまでお願いいたします。】
JASA 日本エリアマネジメント支援協会
info@japan-asa.com