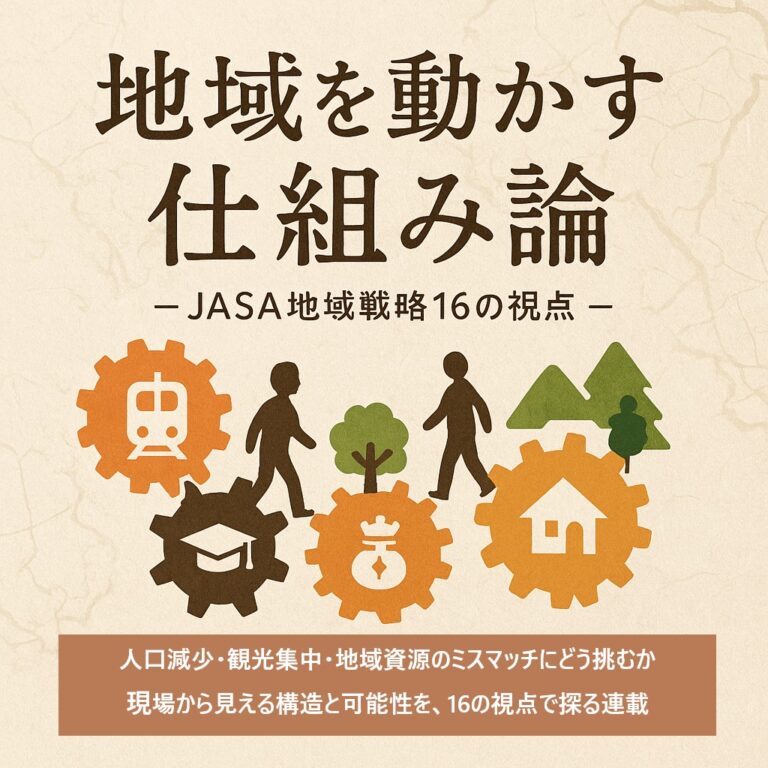1.地域の“中間支援機能”としての役割と現実

商工会議所・商工会は、長年にわたり地域の経済活動を支える“中間支援機能”として重要な役割を担ってきました 。中小企業への経営相談や地域イベントの企画、行政との調整役など、その活動は多岐にわたります 。しかし近年、会員の減少や後継者不足、事業のマンネリ化といった課題が顕在化し、「なくてはならない存在だが、具体的に何をしているのかわかりにくい」と認識されがちです 。本来の存在意義を取り戻すためには、今こそ“役割の再定義”が必要な時期に差し掛かっているのかもしれません 。
2.信頼される支援機関に必要なもの
商工会議所・商工会は、地域事業者にとって“もっとも身近な相談先”であるはずです 。しかし現場では、「当たり障りのない助成金を紹介されただけだった」「提案内容が現場の状況とずれている」といった不満の声も聞かれます 。
こうしたミスマッチの背景には、職員の人数不足や、次々と変わる制度への対応の遅れ、そして事業者と行政・金融機関との間で板挟みになる構造的なストレスがあります 。それでも、地域の変化に最も早く触れているのは、まさにこうした中間支援機関です 。だからこそ、本当に信頼される支援機関になるためには、相手の言葉の真意をくみ取る「聞く力」、多様な立場の論理を理解し、つなげる「翻訳する力」、そして、長期にわたって寄り添い続ける「伴走する覚悟」が問われているのです 。
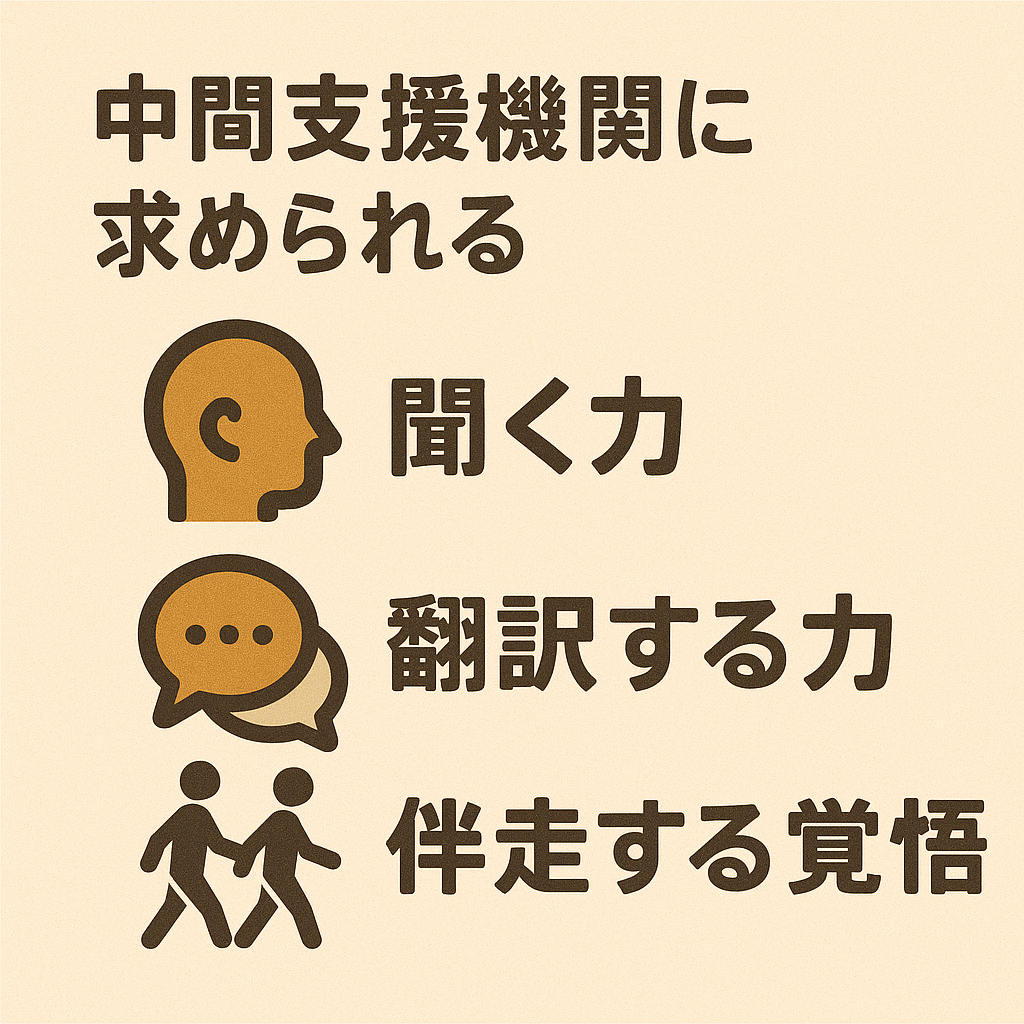
3.JASAが期待する“次世代型支援者像”
JASAは、商工会議所・商工会がこれからも地域に必要不可欠な存在であり続けると信じています 。一方で、組織としての限界や制度の制約が多い現実に対しては、柔軟な“外部との連携”や“役割分担”が求められる時代だと認識しています 。
次世代の中間支援機能は、単なる“窓口”ではなく、地域を動かし、つなぐ“戦略家”としての力が必要です 。行政の論理と地域事業者の本音をうまく「翻訳」し、持続可能な形で政策と経営を結びつけるハブとなること 。そのためには、これまでの“制度案内人”から、地域と共に“仕組みを創り出す共創者”へと進化することが求められます 。JASAは、そうした商工会議所・商工会のアップデートをともに支援しながら、地域の現場で機能する“共創ネットワーク”の形成に取り組んでいきます 。
2025年9月16日
次回予告
次回のテーマは「観光人材“不足”ではなく“設計ミス”ではないか?」です 。人材が足りないのではなく、本来の力が“活かせていない構造”を見直す視点から、観光の現場を考えます 。 ご意見やご感想、または次回のブログ原稿についてお考えがあれば、ぜひお聞かせください。
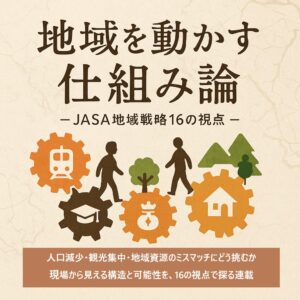
【お問い合わせはこちらまでお願いいたします。】
JASA 日本エリアマネジメント支援協会
info@japan-asa.com