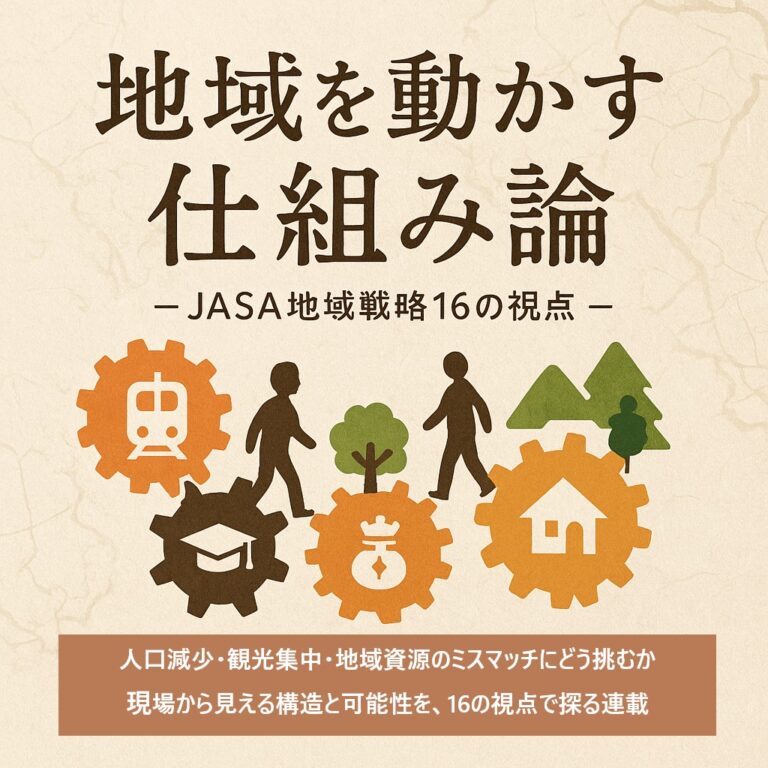1.人材が足りない…本当にそうだろうか?
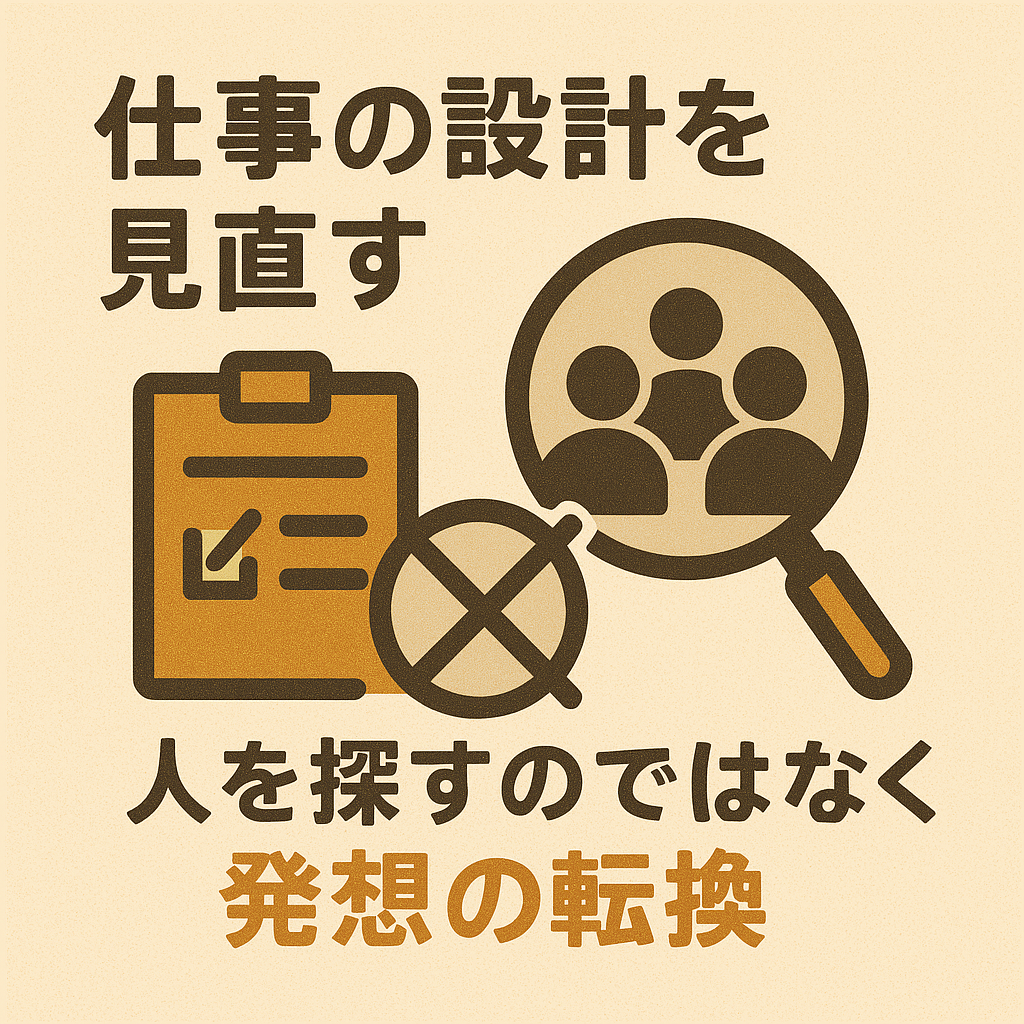
観光地や地域のイベント現場では、しばしば「人手が足りない」「担い手がいない」という声が聞かれます。コロナ禍以降、接客業やサービス業から離れた人材が戻ってこないという実情も確かにあります。
しかし、現場の話を丁寧に聞いてみると、「やりたくないのではなく、やれる形がない」「報われない仕事だから避けている」という声も少なくありません。人手不足という言葉の裏側に、「なぜこの仕事は担い手が戻ってこないのか」という問いが潜んでいるのです。
人が足りないというより、“仕事の設計自体”がずれているのではないか──その視点がいま求められています。必要なのは「人を探すこと」ではなく、「その仕事に人が集まるように設計を変える」発想の転換です。
2.「役割の見直し」と「分解設計」の視点
観光の現場では、ひとつの担当者に複数の業務が集中しすぎていることが珍しくありません。企画、受け入れ、案内、トラブル対応までを一人で担うような構造は、疲弊を生み、人が定着しない最大の要因です。
ここで必要なのは、“業務の分解”と“再設計”です。たとえば、案内と管理、接客とSNS広報を分けて役割を分担することで、それぞれの得意分野が活かされ、人が離れにくい職場づくりにつながります。また、仕事の幅を持たせるより、明確な責任範囲を設けることで安心感が生まれ、現場への信頼も高まります。
さらに、育成の場を設けず“できる前提”で業務を任せてしまう風潮も見直しが必要です。設計を見直すことで、「人材不足」の根本原因が“構造の未整備”だったと気づくこともあります。
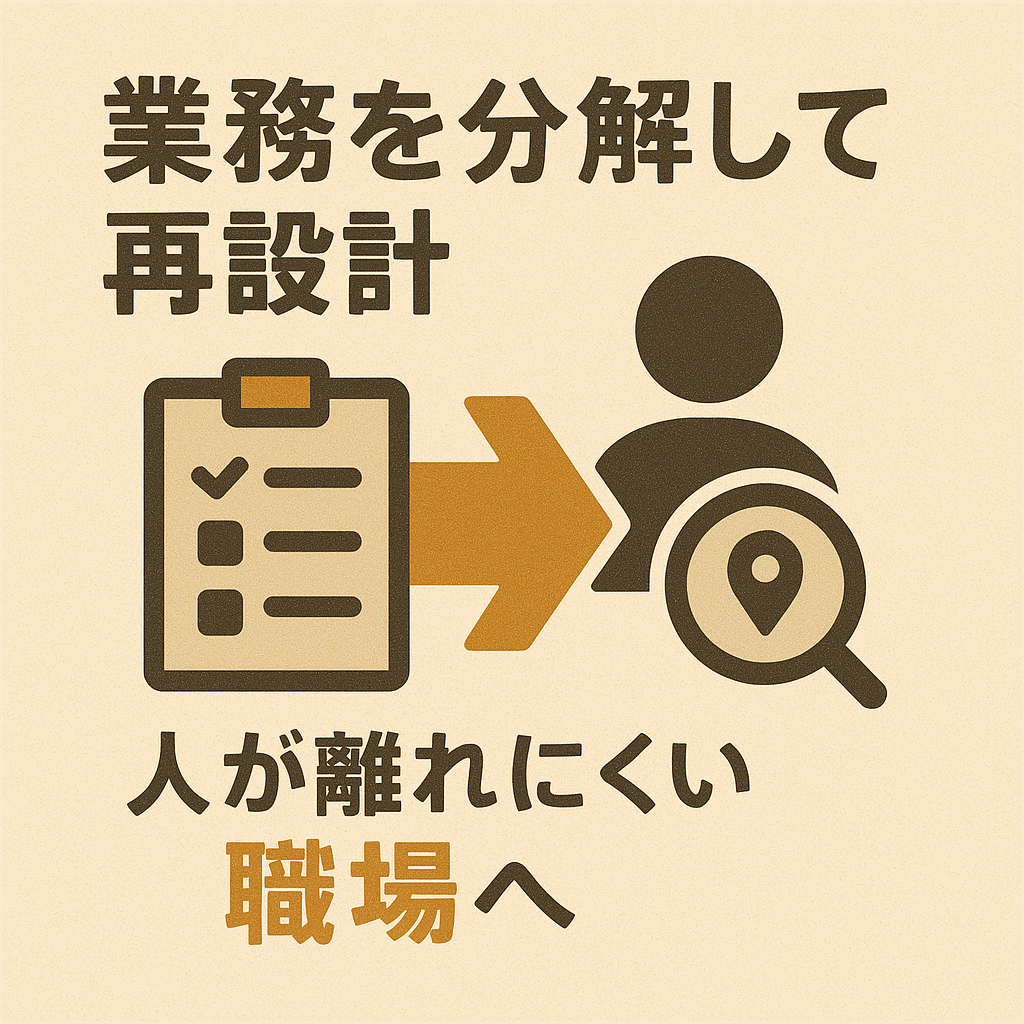
3.JASAの視点と“仕組みの再編集”
JASAでは、“人がいない”を起点にするのではなく、“なぜその役割が回っていないのか”を掘り下げることを大切にしています。単なる求人支援ではなく、業務設計やチーム体制、外部委託の整理、リーダーの育成支援など、仕組みそのものに向き合う支援を行っています。
また、観光人材を“専門職”として捉え直すことも重要です。接客・地域案内・安全管理・PR・商品開発など、多様なスキルが求められる中で、本来は“育て、活かし、報いる”べき価値ある仕事です。
JASAは、観光人材不足という表面的な課題の裏にある“構造の設計ミス”を正面から見つめ、地域と共に“働き続けられる現場づくり”に向けた仕組みをともに考え続けてまいります。
2025年10月1日
次回予告
次回 のテーマは「“定着しないDX”を変える、地域現場の再設計」。
机上の計画ではなく、“使われるDX”にするためのステップを現場視点から掘り下げます。
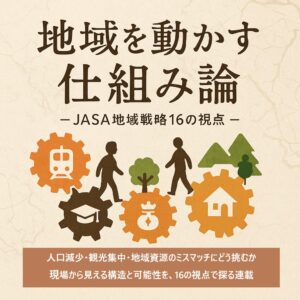
【お問い合わせはこちらまでお願いいたします。】
JASA 日本エリアマネジメント支援協会
info@japan-asa.com